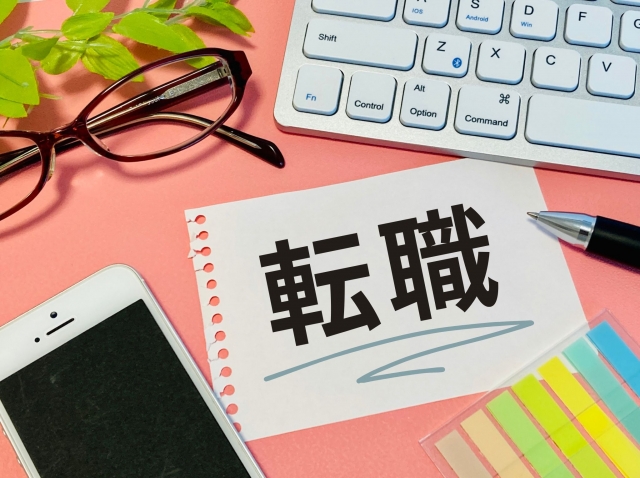【完全版】特定技能「介護」を受け入れるには?雇用の条件や注意点を解説
目次
少子高齢化が進む日本社会では、外国人労働者の雇用が人的リソースを確保するカギになるといわれます。現在外国人労働者を積極的に雇用する企業は増え、企業側の「外国人労働者を採用する」というハードルは下がっていると言えるでしょう。
現場の人材不足に悩んでいるのであれば、特定技能「介護」の制度に基づいた外国人の雇用を検討してみてはいかがでしょうか。特定技能制度を使って本格的に採用を進めるとなると、知っておくべき要件や制度、メリット・デメリットが存在します。
本記事では特定技能「介護」の制度の詳細や雇用の方法、任せられる業務の種類について詳しくご紹介します。
特定技能人材の採用なら、取引社数100社以上の「スキルド・ワーカー」で
スキルド・ワーカーを運営する株式会社リクルーティング・デザインは、リクルート正規代理店として30年以上の実績を持つ人材紹介会社です。2019年4月に特定技能制度が新設された当初から、500名以上の外国人材を紹介してきました。もしも現在、
・複数ある特定技能サービスから何を選んで良いかが分からない
・外国人材への必要なサポートが不安
・採用・労務運用の手間をなるべく削減したい
・大量採用を検討している
スキルド・ワーカーなら、これらの課題をすべて解決できます!人材の紹介はもちろん、入国手続きや生活支援、日本語教育、資格取得支援など、義務化されている外国人材への支援もすべてお任せしていただけます。
特定技能「介護」とは外国人労働者が介護事業所で働ける在留資格
特定技能とは、日本国内で人手不足が起きている分野において、相当の知識や技能を有する外国人労働者を受け入れる在留資格のことです。従来よりもゆるやかな条件で外国人を雇用できるのが特定技能の特徴です。
特定技能の制度が導入されたのは2019年4月のことです。その対象となるのは、慢性的に人手が足りなくなりがちな農業や建設、漁業、外食業などの分野です。そして、介護の分野でも人手不足が顕著であることから、『特定技能「介護」』として介護職で就労することを前提にした外国人材が取得する在留資格の制度が適用されています。
特定技能は、外国人の「技能実習」と混同されることがあります。しかし、特定技能の制度は教育や研修を目的としたものではありません。この制度ではあくまで、介護施設で働ける即戦力となる人材を求めることを主眼としています。そのため、特定技能「介護」の制度に基づいて雇用を行う際には、十分な介護技能や日本語能力を有している人材を選ぶことが必要です。
他にも特定技能制度と技能実習では11もの違いがあります。詳しく知りたい方は、別記事「特定技能と技能実習は違う!どこが違うの?メリットデメリットを解説します」もご覧ください。
特定技能には1号と2号の2種類があります。このうち、特定技能「介護」では1号のみを適用できます。特定技能2号は更新の上限がなく、要件を満たせば永住権を獲得したり家族を帯同したりといった働き方も可能です。
特定技能「介護」が該当する特定技能1号は、在留期間を通算5年までと定めています。また、家族の帯同は認められていません。ほかに、技能水準や日本語能力水準に一定の基準が設けられています。
特定技能「介護」では基本在留期間を1年と設定しています。期間は6カ月か4カ月で更新でき、最長5年までの延長が可能です。
特定技能「介護」が設立された背景
日本国内の介護の現場では深刻な人手不足が起きています。厚生労働省によると、2025年度の時点で約37.7万人もの介護人材が不足すると試算されています。実際に、大多数の事業所において介護に従事できる従業員が不足しているのが現状です。
少子高齢化が急激に進む日本で、今後の介護利用ニーズが激増することは疑いようがありません。日本国内で介護に従事する職員が不足する理由は、採用が難しい点にあります。介護のニーズが高まっていることから、同業他社との人材獲得競争に悩む事業所も増加しています。
また、介護従事者の労働条件や待遇があまりよくないことも、人材不足に拍車をかけている理由です。ハードな仕事であるにもかかわらず、十分な報酬を得られないケースも多く、転職や離職に踏み切る人も少なくありません。実際に、介護従事者のうち勤続3年未満で離職する人は6割を超えているといわれます。
特定技能「介護」の制度は、介護の現場における雇用の問題を改善する切り札として期待を集めています。政府は特定技能の計画を立てた2019年当初、2024年までに介護分野において6万人の特定技能外国人労働者を受け入れるという目標を掲げていました。
しかし、新型コロナウイルス感染症にともなう入国制限が大きな痛手となり、思ったような特定技能労働者の受け入れができていません。2022年以降には入国制限が緩和されることから、特定技能外国人労働者も少しずつ受け入れやすくなることが期待されています。
任せることができる業務内容
特定技能「介護」の外国人受け入れには一定の条件があります。特定技能「介護」で外国人を雇用するときには、任せられる業務の範囲や制限を確認しておくことが重要です。
特定技能「介護」で外国人を雇用するときには、介護に関わる業務に従事させる必要があります。例えば、利用者の入浴・食事の介助などの身体介護業務、レクリエーションの実施や機能訓練の補助などを任せることが可能です。また、これらに付帯する業務を任せられます。そのため、介護老人福祉施設や介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護、有料老人ホームなどでは特定技能「介護」の人材を多く受け入れており、外国人材が活躍しています。
ただし、訪問系の介護サービスは対象外となっており、に従事させることはできません。そのため、訪問介護事業所では特定技能の外国人を受け入れることができないので注意しましょう。
また住居型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅のように介護サービスを提供しない施設でも、特定技能の外国人の雇用は不可とされています。以下は、特定技能「介護」人材を受け入れられる施設と受け入れられない施設の一例です。
受け入れ可能施設
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 認知症対応型共同生活介護
- 有料老人ホーム
受け入れNG
- 訪問系の介護サービス
- 住居型有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
※参照:介護分野の1号特定技能外国人を受け入れる対象施設について|厚生労働省
特定技能「介護」を受け入れる基準や要件
特定技能「介護」を取得している外国人材は対応可能な業務が幅広いため、即戦力として期待できます。しかし、人材を受け入れる際には満たすべき基準や、守るべき要件があります。ここからは、特定技能「介護」を受け入れる基準や要件について解説します。
受け入れ機関に求められる基準
出入国在留管理局庁は特定技能受け入れ機関に向けて、「特定技能外国人受け入れる際のポイント」という資料を発布しています。この資料によると、特定技能の受け入れ機関には以下のような基準や条件が求められています。
「受入れ機関自体が満たすべき基準」
- 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
- 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
- 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
- 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
- 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備え置くこと
- 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
- 受入れ機関が保証金の徴収等を定める契約等を締結していないこと
- 支援に要する費用を、直接又は間接に外国人に負担させないこと
- 労働者派遣をする場合には、派遣元が該当分野に係る業務を行っている者などで、適当と認められる者であるほか、派遣先が1〜4の基準に適合すること
- 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
- 雇用契約を継続して履行できる体制が適切に整備されていること
- 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
- 分野に特有の基準に適合すること
※ 引用:出入国在留管理庁|特定技能外国人受け入れる際のポイント
特定技能の外国人労働者を受け入れられるのは、上記の基準を満たしている企業に限られます。数多くの項目がありますが、ほとんどの項目には基本的なことが記されています。
例えば社会保険や税法のルールを守っていることや法令に違反していないことなどの項目については、遵守するのはそれほど難しくありません。特定技能の制度を活用する際には、給与支払いの方法や保険関係の届出など、受け入れ条件を十分に確認した上で正しい運用が求められます。
その他受け入れ期間に必要な要件について、別記事「特定技能を持った外国人の受け入れ機関になる為に必要なこととは?」で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
フルタイムの直接雇用のみ認められる
特定技能「介護」の外国人の雇用条件は直接雇用のみです。派遣社員などの形で仕事をしてもらうことはできません。また、アルバイトやパートといった雇用形態も認められていません。特定技能の外国人を雇う際には、フルタイムの直接雇用の形態を選びましょう。
日本人社員と同等以上の報酬が必須
特定技能の外国人を雇用する際には、同じ業務に従事している日本人等の常勤介護職員と同等またはそれ以上の報酬額を設定しなければなりません。また、福利厚生に関しても同等のものを用意しましょう。従業員の国籍に関係なく、平等な雇用をおこなうことが重要です。
受け入れ人数や期間が制限されている
一つの事業所において、日本人等の常勤介護職員の総数を超えた特定技能の外国人を雇用できません。ただし、この日本人等のくくりには、EPA介護福祉士や在留資格「介護」により在留する外国人が含まれます。また、永住権を持つ外国人や日本人の配偶者にあたる外国人なども日本人等の範囲内です。技能実習生や留学生、EPA介護福祉士候補者は含まれません。
つまり受け入れられる人数は次のようなイメージとなります。
| 現在の職員数 | 受け入れ可能な特定技能の人数 | |
| 例1 | 日本人の常勤介護職員が3人の場合 | 3人 |
| 例2 | 日本人の常勤介護職員が2人、パートが1人の場合 | 2人 |
| 例3 | 日本人の常勤介護職員が2人、日本人の配偶者をもつ外国人常勤介護職員が2人の場合 | 4人 |
また、特定技能の外国人の受け入れ期限は上限5年です。期間満了後には在留資格がなくなるため外国人労働者は帰国しなければならなくなります。
事業所は専門の協議会への加入が必要
特定技能「介護」で外国人を雇用する企業は、「介護分野における特定技能協議会」への加入が求められます。加入の申し込みは厚生労働省のホームページからおこなうことが可能です。
加入申請には雇用条件書や1号特定技能外国人支援計画書、介護分野における業務をおこなわせる事業所の概要書等、労働者の日本語能力水準を証明する書類、技能水準を証明する書類、在留カード等の書類が求められます。加入の期限は特定技能「介護」で外国人労働者を雇用してから4カ月以内のため、期限を過ぎないよう十分注意しましょう。
雇用した外国人への支援を適切におこなうことも大切
特定技能「介護」で外国人を受け入れる企業には、法律で定められた支援を適切におこなうことが義務となります。業務面でも生活面でも外国人材が安心して過ごせるように支援することが重要です。社内で体制の構築をおこなうほか、登録支援機関に支援を委託する方法を選んでも問題ありません。
外国人採用をまるごとおまかせできるスキルド・ワーカー
2019年の特定技能精度スタートからこれまでに、介護施設、飲食店に130名を超える紹介実績があるスキルド・ワーカーなら、特定技能外国人材の採用から受入れ・支援までワンストップでサポートします。
お電話かメールでお気軽にご相談ください!
長年培ってきた採用ノウハウで、特に、介護・外食・飲食料品製造・宿泊・農業での外国人材のベストマッチングを実現します。まずはお問い合わせフォームから、ご相談ください。お困りごとに対して、最適なご提案をさせていただきます。
外国人材が特定技能「介護」を取得する試験条件
外国人が特定技能「介護」の制度に基づいて介護の現場で働くためには、規定の試験に合格する必要があります。技能水準と日本語能力の水準を満たしていることが、特定技能「介護」の適用条件です。ここからは、特定技能「介護」を適用する際に求められる試験の内容を解説します。
- 介護技能評価試験
- 日本語能力試験または国際交流基金日本語基礎テスト
- 介護日本語評価試験
1. 介護技能評価試験
介護技能評価試験は厚生労働省が主導する試験で、特定技能外国人の介護技能水準を見極めることを目的としています。介護分野で仕事をするためには一定の介護技能が必要です。特定技能「介護」では、介護業務の基盤となる考え方に基づいて、利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベルを求めています。
介護技能評価試験は介護の基本、心と体の仕組み、コミュニケーション技術、生活支援技術の4つのカテゴリから出題されます。試験は日本国内のほか、諸外国でも実施され、試験には実施国の現地の言語が使われます。学科試験40問に加え、実技試験も5問出題されます。合格率は毎回6~7割前後となっています。
2. 日本語能力試験または国際交流基金日本語基礎テスト
日本で働くためには、ある程度日本語を話すことが求められます。特定技能「介護」の適用となるためには、日常会話ができ生活に支障がない程度の日本語能力を身につける必要があります。
日本語能力試験(JLPT)N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)のA2に合格すれば、必要な日本語能力の水準を満たしていると判断されます。自身のことや身の回りのことなどを簡単な言葉で説明できる日本語力があれば合格が可能です。
3. 介護日本語評価試験
介護現場で頻繁に使用する日本語を問題なく使いこなせるかも重要なポイントです。特定技能「介護」を適用するためには、介護日本語評価試験に合格しなければなりません。介護現場では利用者に対する声かけや会話などが求められます。
現場に特化した日本語を使いこなせることも、制度適用の条件です。介護日本語評価試験は日本国内の各試験会場に加え、フィリピンやタイ、ミャンマーなど各国の会場でも受けられます。合格率は80%前後です。
一定の経歴や資格があれば試験が免除される
特定技能「介護」の適用のためには基本的に上記の試験を受ける必要がありますが、一定の経歴や資格があれば試験が免除されることもあります。
例えば介護における技能実習2号を終了している人は、技能実習修了証を提出したのち介護の仕事に就くことができます。技能実習2号の取得のためには、日本の介護の現場において3年以上の実習勤務が必要です。実習が修了していれば、相応の介護技術があると判断されるのです。
また、EPA介護福祉士候補者も規定の試験を受ける必要がありません。EPA介護福祉士は日本の介護福祉士資格を目指す外国人のことを指します。指定養成施設で4年間の研修や勤務をおこない、さらに介護福祉士国家試験で5割以上の得点を取っていれば、十分な専門性があると判断されます。介護福祉士国家試験結果通知書を提出すれば、介護現場で勤務できます。
ほかに、介護福祉士養成課程を修了している外国人も試験免除の対象となります。医療福祉専門学校や大学で介護の課程を修了しているのであれば、十分な技能が身についていると認められます。この場合には卒業証明書を提出することで勤務が可能です。
特定技能「介護」に基づいて外国人を雇用するメリット
介護の事業所で外国人労働者を雇用するのなら、特定技能「介護」の制度の利用がおすすめです。特定技能「介護」の活用には以下のようなメリットが考えられます。
- 働いてもらう上での制限が少ない
- 新設要件が設定されていない
- 雇用できる人数が多い
- 即戦力となる人材を雇用できる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1. 働いてもらう上での制限が少ない
EPA介護福祉士や在留資格「介護」では、資格取得に長い時間や大きなコストがかかってしまいます。特定技能「介護」であれば、試験に合格した外国人にすぐに働いてもらうことが可能です。
技能実習の場合には報告に手間がかかりますが、特定技能「介護」であれば細かく報告をおこなう必要もありません。特定技能「介護」は訪問系のサービスには適用できませんが、ほかの介護系事業であれば幅広い範囲で活躍してもらえます。
就業上の制約や制限もほとんどなく、管理にあたって負担がかからないのは、特定技能「介護」の大きなメリットです。
2. 新設要件が設定されていない
EPA介護福祉士や技能実習という形で外国人を雇用する場合には、新設要件に該当することがあります。これらの雇用形態では、介護の事業所を新設してから3年以内は外国人を雇用できないのです。
しかし、特定技能「介護」には新設要件が設定されていません。新しく立ち上げたばかりの事業所で、事業を軌道に乗せるために外国人を雇用したい場合には、新設要件のない特定技能「介護」の制度活用がおすすめです。
3. 雇用できる人数が多い
技能実習などの形で外国人を雇用する場合、人数には厳しい制限が設けられています。
例えば常勤の介護職員が30名いる事業所では、技能実習を3名までしか受け入れることができません。特定技能「介護」の制度ではこれよりも多く、在籍する常勤の介護職員と同じ人数の30人の外国人を雇用できます。制度を活用すれば、事業所の人材不足を一気に解消することも可能です。
4. 即戦力となる人材を雇用できる
特定技能「介護」を活用すれば、十分な知識やスキルを持つ人材を即戦力として雇い入れることができます。技能実習の場合、講習や研修の受講中はどうしても研修生のような扱いになってしまいます。
また、講習費用や講習中の生活費などは受け入れる事業所が負担しなければなりません。技能実習の形で外国人を雇用しても即戦力とならず、費用ばかりがかかってしまうケースも事業所によっては発生します。
特定技能「介護」を利用して働く外国人は、介護技術評価試験や日本語能力試験を受けることが求められています。これらの試験に合格している人材であれば、すぐに業務にあたってもらうことができます。
特定技能「介護」で外国人を雇用するデメリット
特定技能「介護」での雇用には多くのメリットがありますが、一方でデメリットも考えられます。特定技能「介護」の活用には以下のようなデメリットがあるでしょう。
- 転職の可能性がある
- 外注費用や給与が高くなることがある
- 働ける期間が制限されている
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1. 転職の可能性がある
技能実習やEPA介護福祉士で外国人を受け入れた場合、労働者は基本的にその事業所で働き続けることになります。
しかし、特定技能「介護」には転職の制限がありません。ほかに待遇のよい介護施設や事業所があった場合、外国人労働者がそちらに転職してしまうおそれもあります。
優秀な人材の転職を防ぐためにも、十分な待遇を用意したり生活のサポートをしたり、利用者とのコミュニケーションを円滑にする対策をとるなどの対応が必要です。
2. 外注費用や給与が高くなることがある
特定技能「介護」で外国人を雇用するときには、登録支援機関などを活用するケースが多いです。こういったサポートの利用には一定の費用がかかります。場合によっては外国人雇用をきっかけにコストがかさんでしまうことがあるかもしれません。
また、特定技能「介護」で雇用する外国人は十分な知識やスキルを持っていることから、賃金の額も高くなる傾向があります。技能実習などの費用に比べ、給与額が高くなりがちな点も把握しておきましょう。
3. 働ける期間が制限されている
特定技能「介護」で雇用する外国人が在留できる期間は、現状のところ5年間に制限されています。政府は特定技能を1号と2号に分類しており、2号では更新をすれば期限の定めなく外国人を雇用し続けることができます。
しかし、特定技能2号は現在介護の分野には適用されていません。とはいえ、介護の現場で深刻な人手不足が起きている現状を考えれば、今後在留期間が伸びる可能性は十分考えられます。
なお、特定技能「介護」に加え、技能実習1号、2号、3号の制度を利用すれば、最長で10年にわたって就労してもらえます。また、介護福祉士試験に合格すれば在留期間の定めなく介護業界で働くことが可能です。
特定技能「介護」で外国人労働者を探す方法
特定技能「介護」の外国人労働者は、求人媒体などを使って探すことができます。特定技能の希望者が集まりやすい求人媒体を選び、求人広告を出してみましょう。
また、人材紹介会社に依頼してサポートしてもらう方法もあります。外国人雇用に強い人材紹介会社を選んで依頼すれば、特定技能「介護」の労働者が見つかりやすくなります。また、人材の紹介や採用活動だけでなく、手続きのサポートまでを受けることができるかもしれません。
| 登録支援機関とは?
登録支援機関とは、外国人を雇うに当たって必要な手続きや、外国人に対するサポートの手伝いを委託できる機関のことを指します。 |
特に初めて特定技能「介護」の外国人雇用をおこなう際には、手続きの煩雑さに雇用までに時間がかかってしまうことも懸念されます。十分なノウハウを持つ人材紹介会社の手を借りれば、いい人材をスムーズに採用できます。
外国人採用をまるごとおまかせできるスキルド・ワーカー
2019年の特定技能精度スタートからこれまでに、介護施設、飲食店に130名を超える紹介実績があるスキルド・ワーカーなら、特定技能外国人材の採用から受入れ・支援までワンストップでサポートします。
お電話かメールでお気軽にご相談ください!
長年培ってきた採用ノウハウで、特に、介護・外食・飲食料品製造・宿泊・農業での外国人材のベストマッチングを実現します。まずはお問い合わせフォームから、ご相談ください。お困りごとに対して、最適なご提案をさせていただきます。
外国人介護職員を受け入れる際の注意点
特定技能「介護」の外国人介護士を受け入れるにあたって気をつけておきたいポイントはいくつもあります。ここからは、受け入れの条件や気をつけたいポイントを確認していきましょう。
1. 法令を満たしていなければ受け入れができない
事業所が法令を遵守していることは、特定技能「介護」を適用するための重要なポイントです。厚生労働省は、特定技能「介護」の適用条件について、企業が労働関連の法令を遵守していることを挙げています。また、社会保険や租税関係法令を遵守していること、5年以内に出入国や労働法令違反がないこと、1年以内に労働者を解雇などの形で離職させていないことも条件となります。
特定技能「介護」の制度を活用する際には、雇用に関する問題が起きていないかをチェックしていきましょう。
2. 外国人雇用には一定の費用がかかる
特定技能「介護」の外国人雇用にはある程度の費用がかかります。例えば人材紹介会社を利用した場合には紹介料が求められますし、求人広告を出すときには掲載料がかかります。これに加え、登録支援機関を利用するときには業務委託手数料が必要です。業務委託手数料の業界相場は3万円前後となっています。
ただし、外国人材の雇用には、業務面でも生活面でも外国人材が安心して過ごせるように支援することが義務付けられています。初めて外国人材の雇用をする企業は、業務面や生活面の支援に戸惑ってしまうこともあるかもしれません。時間的なコストがかかりすぎてしまうようであれば、費用をかけて登録支援機関への依頼を検討してみてもいいかもしれません。
3. 外国人の就労や生活の支援が必要
特定技能「介護」で外国人を受け入れるときには、労働者の就労支援や生活支援をおこなうことが求められます。出入国の送迎や住居の確保、公的手続きへの同行といった一連の準備のほか、相談への対応や日本人との交流促進、面談の実施などの対応も必要です。
これら一連の対応に時間を割くのが難しいときには、専門の登録支援機関への委託も可能です。登録支援機関とは、特定技能外国人の就業施設から依頼を受け、外国人の支援を全面的にバックアップする機関のことです。十分なノウハウを持つ専門のスタッフが外国人のサポートをしてくれるので安心できます。
4. 特定技能協議会への加入を義務付けられている
特定技能資格者を受け入れる事業所は、分野別特定技能協議会への加入が義務付けられます。介護技能協議会は、所轄省庁や関係省庁、業界団体、学識者などで構成されています。協議会は制度の趣旨や構造の周知、コンプライアンス啓発、情勢の把握や分析、受け入れの調整などのさまざまな活動をおこなっています。
特定技能協議会への加入期限は雇用する外国人が入国してから4カ月以内となっています。早めに書類を用意し、協議会事務局のオンラインシステムで申請をおこないましょう。
5. 外国人受け入れ事業を活用する方法もある
特定技能で介護人材を円滑に雇用するため、外国人介護人材受け入れ観光整備事業が創設されました。外国人介護人材受け入れ観光整備事業では、介護技能評価試験の実施や外国人介護人材受け入れ支援の事業を実施しています。
また、日本語学習の支援や各種相談の支援なども行われています。こういった制度を利用すれば、特定技能「介護」における外国人雇用をスマートに進められるでしょう。
6. 試験に合格した証明書が必要になる
特定技能「介護」で外国人を雇用する際には、所定の書類を提出するなどの準備が必要です。必ず提出しなければならない書類には以下のようなものがあります。
- 介護技能評価試験の合格証明書の写し
- 介護日本語評価試験の合格証明書の写し
- 日本語能力を証するものとして次のいずれかの写し(国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書、日本語能力試験N4以上の合格証明書、介護福祉士養成施設の卒業証明書の写し)
また、外国人介護職員が介護福祉士国家試験に合格している場合には、結果通知書の写しも提出します。ほかにも、契約内容や報酬に関する説明書や確認書、特定技能協議会の構成員であることを証明する書類などを求められることもあるので、必要書類を過不足なく揃えて申請しましょう。
特定技能「介護」の外国人労働者を雇用しよう
現在日本国内では、深刻な人手不足の対策法として外国人材を受け入れる特定技能が推進されています。とくに介護の分野では人手不足が深刻化していることから、積極的に外国人材を雇用する動きが広がっています。
特定技能「介護」の良さは、即戦力となる外国人介護職員を雇用できる点です。特定技能「介護」で雇用する外国人には現場で必要な日本語能力も身についているため、コミュニケーションを取るうえでの心配もほとんどありません。また、制限も少なく、雇用した後すぐにさまざまな業務を教えられる点は他の職員にとっても大きなメリットになります。
特定技能「介護」で外国人を雇用する際には一定の手続きが必要です。事業所内で手続きの処理をするのが難しいときには、専門機関や登録支援機関に依頼するなどの方策を講じましょう。
特定技能人材の採用なら、取引社数100社以上の「スキルド・ワーカー」で
スキルド・ワーカーを運営する株式会社リクルーティング・デザインは、リクルート正規代理店として30年以上の実績を持つ人材紹介会社です。2019年4月に特定技能制度が新設された当初から、500名以上の外国人材を紹介してきました。もしも現在、
・複数ある特定技能サービスから何を選んで良いかが分からない
・外国人材への必要なサポートが不安
・採用・労務運用の手間をなるべく削減したい
・大量採用を検討している
スキルド・ワーカーなら、これらの課題をすべて解決できます!人材の紹介はもちろん、入国手続きや生活支援、日本語教育、資格取得支援など、義務化されている外国人材への支援もすべてお任せしていただけます。