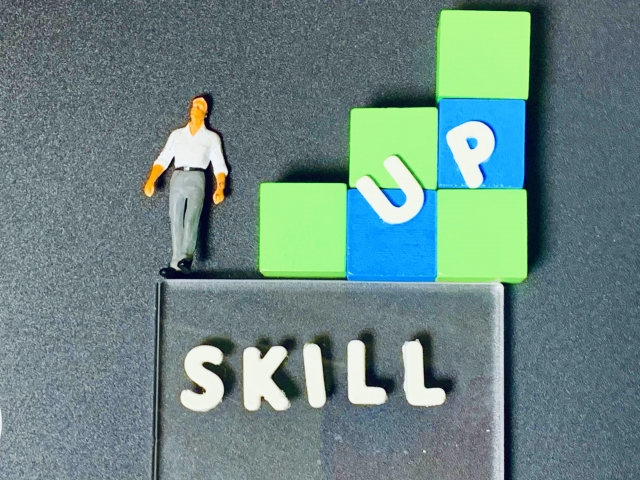【事業者向け】脱退一時金制度とは?外国人労働者が支払った厚生年金はどうなるの?
日本国内に住所を所有しており、年齢が20歳以上60歳未満である場合は、国民年金や厚生年金の被保険者となります。[注1]
国籍の要件はなく、上記に該当する外国人であれば、日本人と同様に年金を支払う必要があります。なお、医療滞在ビザや長期観光ビザで滞在している外国人は含みません。
長期に渡って日本に滞在するのではなく、数年で母国へ帰国してしまう外国人は多いです。たとえば、技能を習得するために日本へ来ている外国人労働者や、語学を学びに日本へ来ている留学生の場合は、目的を達成したら母国へ帰国したり他国へ移住したりする方も多いでしょう。
その際に該当する外国人が日本から離れて、年金を受け取れなくなるケースは少なくありません。そのために設けられているのが、脱退一時金制度です。
本記事では、外国人労働者や留学生が支払った厚生年金はどうなるのか、脱退一時制度とは何かについて解説します。
[注1]日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 被保険者のしおり」
そもそも脱退一時金制度とは?
日本国内に住所を所有している外国人は、基本的に国民年金や厚生年金の被保険者となります。しかし、厚生年金の保険料を支払っても、数年後に保険料が還元されるわけではなく、65歳以降にならないと受け取れません。[注2]
仮に期間前に母国へ帰ったり他国へ移住したりする場合は、納めてきた年金保険料が無駄になってしまいます。そのため、日本では厚生年金の保険料の掛け捨てをならないよう脱退一時金制度が設けられています。
脱退一時金制度とは、老齢年金の受給資格期間10年を満たさずに帰国・移住した場合に、すでに納めている年金保険料のうち一部分を返してもらえる制度です。
留意点として、厚生年金保険に6カ月以上加入したことがある外国人が対象者であり、日本を出国後2年以内に日本年金機構に請求する必要があります。[注3]
[注3]日本年金機構「脱退一時金の制度」
脱退一時金が支給される要件
脱退一時金が支給される要件は下記の通りです。[注4]
- 厚生年金保険の加入期間が6カ月以上である
- 日本国籍を有してない外国人である
- 日本の住所を有していない
- 老齢年金の受給資格である10年に達していない
- 障害手当金を受ける権利を持ったことがない
上記の条件に全て当てはまり、日本を出国後2年以内に日本年金機構に請求すれば、脱退一時金が支給されます。
ポイントとしては、日本に住民票・住所がないことと、受給資格がないことです。スムーズに脱退一時金を支給してもらうために、日本を出国する際は、事前に住民票がある市町村で転出届を出しておくとよいでしょう。
[注4]日本年金機構「脱退一時金の制度」
脱退一時金で受け取れる金額
厚生年金保険の脱退一時金の支給額は下記の計算式を用いて算出します。[注5]
|
被保険者であった期間の平均標準報酬額×支給率(保険料率×2分の1×支給率計算に用いる数) |
被保険者期間であった期間の平均標準報酬額は、下記2つを合算した額を全体の被保険者期間の月数で割った額です。
- 2003年4月より前の被保険者期間の標準報酬月額に3を乗じた額
- 2003年4月以後の被保険者期間の標準報酬月額および標準賞与額を合算した額
支給率は資格喪失した日の属する月の前月と、被保険者であった期間によって変わります。具体的には以下のとおりです。
【最終月が2022年(令和4年)4月以降の場合】
|
被保険者であった期間 |
支給率計算に用いる数 |
支給率 |
|
6カ月以上12カ月未満 |
6 |
0.5 |
|
12カ月以上18カ月未満 |
12 |
1.1 |
|
18カ月以上24カ月未満 |
18 |
1.6 |
|
24カ月以上30カ月未満 |
25 |
2.2 |
|
30カ月以上36カ月未満 |
30 |
2.7 |
|
36カ月以上42カ月未満 |
36 |
3.3 |
|
42カ月以上48カ月未満 |
42 |
3.8 |
|
48カ月以上54カ月未満 |
48 |
4.4 |
|
54カ月以上60カ月未満 |
54 |
4.9 |
|
60カ月以上 |
60 |
5.5 |
【最終月が2017年(平成29年)9月から2021年(令和3年)3月の場合】
|
被保険者であった期間 |
支給率計算に用いる数 |
支給率 |
|
6カ月以上12カ月未満 |
6 |
0.5 |
|
12カ月以上18カ月未満 |
12 |
1.1 |
|
18カ月以上24カ月未満 |
18 |
1.6 |
|
24カ月以上30カ月未満 |
25 |
2.2 |
|
30カ月以上36カ月未満 |
30 |
2.7 |
|
36カ月以上42カ月未満 |
36 |
3.3 |
また、2021年4月の改正により、資格喪失した日の属する月の前月が2021年4月以降の場合は、計算に用いる月数の上限が3年から5年へ変更となりました。
改正の要因として挙げられる点は、以下のとおりです。
- 2019年に追加された在留資格の期間上限が5年であること
- 3年から5年滞在している外国人出国者が一定数いること
[注5]日本年金機構「脱退一時金の制度」
脱退一時金を請求する手続き
脱退一時金を請求する際は、下記2つの書類を提出する必要があります。
- 脱退一時金請求書
- 添付書類等
脱退一時金請求書は、日本語だけでなく下記外国語が併記された様式となっています。
|
英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、インドネシア語、フィリピノ(タガログ)語、タイ語、ベトナム語、ミャンマー語、カンボジア語、ロシア語、ネパール語、モンゴル語 |
脱退一時金請求書は、日本年金機構のホームページからダウンロードすることが可能です。または、ねんきんダイヤルに電話して郵送してもらう方法もあります。
なお、脱退一時金請求書の提出時は、下記の書類を添付しなければなりません。[注6]
|
書類名 |
留意すべき事項 |
|
パスポート(旅券)の写し |
氏名、生年月日、国籍、署名、在留資格のを確認できるページを添付 |
|
日本国内に住所を有しないことが確認できる書類
|
住民票の除票の写しやパスポートの出国日が確認できるページの写しが該当 |
|
受取先金融機関名、支店名、支店の所在地、口座番号、請求者本人の口座名義であることを確認できる書類
|
・金融機関が発行した証明書または請求書の銀行の証明欄に銀行の証明でも可能 ・日本国内の金融機関で受け取る場合、口座名義がカタカナで登録されていることが必要 ゆうちょ銀行および一部インターネット専業銀行では脱退一時金を受け取ることができないため注意 |
|
基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 |
年金手帳を確認 |
|
代理人が請求手続きを行う場合は委任状 |
代理人を通じて請求手続きを行う場合、複数の代理人への委任は行わない |
書類によっては準備に時間を要するものもあったり、日本滞在時に用意する必要があったりするため、事前に準備しておくとよいでしょう。
脱退一時金の請求に関する3つの注意点
脱退一時金の請求に関する注意事項は下記の通りです。
- 脱退一時金の請求以前の年金加入期間が無効となる
- 住所が日本にある場合は脱退一時金を受け取れない
- 帰国前に日本国内から請求書を提出する方法
注意事項をしっかりと理解した上で脱退一時金を申請すれば、スムーズに請求できるでしょう。
脱退一時金の請求以前の年金加入期間が無効となる
脱退一時金を受け取ってしまうと、脱退一時金を請求する以前の年金加入期間がすべて無効となります。出国や移住後に日本に戻る予定がない方であれば問題はありませんが、将来日本に戻ったり日本の老年年金を受け取ったりする可能性がある方は慎重に検討した方がよいでしょう。
また、2017年8月より老齢年金の受給資格期間が25年から10年に短くなりました。[注7]
2017年以前は、10年以上日本に滞在していても脱退一時金を受け取ることができました。現在は10年以上滞在すると受給資格期間を満たすことから、脱退一時金は受け取れないため、注意しましょう。
[注7]日本年金機構「平成29年8月から、老齢年金を受け取るために必要な資格期間が25年から10年以上に変更されました」
住所が日本にある場合は脱退一時金を受け取れない
脱退一時金の請求書を受理した日に、該当者の住所がまだ日本にある場合は、脱退一時金が受け取れません。
対処法として、事前に住民票がある市町村で転出届を届け出ておきましょう。事前に転出届を提出しておけば、出国予定日に住民票が除票扱いとなり、日本に住民票がない状態で出国が可能となります。
帰国前に日本国内から請求書を提出する方法
出国前に日本国内から脱退一時金の請求書を提出する場合、住民票の転出予定日以降に日本年金機構等に提出しましょう。
窓口ではなく郵送で手続きを行う場合は、請求書が転出予定日以降に日本年金機構等に書類が到達している必要があります。
転出届を提出しておらず再入国許可・みなし再入国許可を受けて出国した場合、再入国許可の有効期間が経過するまでは脱退一時金は請求できないので注意しましょう。
【まとめ】
脱退一時金の申請の際は必要書類や注意点を押さえておこう
脱退一時金制度は、老齢年金の受給資格期間10年を満たさずに帰国・移住した場合に、既に納めている年金保険料のうち一部分を返してもらえる制度です。
脱退一時金が支給される要件は下記の通りです。
- 厚生年金保険の加入期間が6カ月以上である
- 日本国籍を有してない外国人である
- 日本の住所を有していない
- 老齢年金の受給資格である10年に達していない
- 障害手当金を受ける権利を持ったことがない
上記の条件に全て当てはまれば、脱退一時金が支給されます。留意点として、日本年金機構等に脱退一時金の請求書を受理した日に、該当者の住所がまだ日本にある場合は脱退一時金が受け取れません。そのため、事前に住民票がある市町村で転出届を出しておくとよいでしょう。事前に転出届を提出しておけば、出国予定日に住民票が除票扱いとなり、日本に住民票がない状態で出国が可能です。
脱退一時金を請求する際は、下記2つの書類を提出する必要があります。
- 脱退一時金請求書
- 添付書類等
書類によっては準備に時間を要するものもあったり、日本滞在時に用意する必要があったりするため事前に準備しておきましょう。