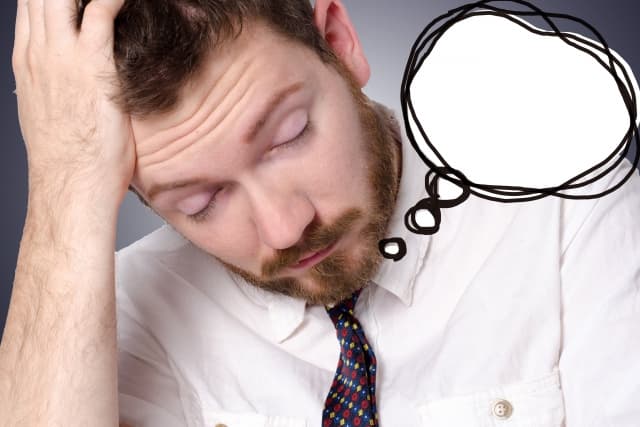特定技能の派遣は農業・漁業のみ可能|業務・条件・費用を解説
特定技能 2023.10.27

目次
原則、特定技能人材では派遣が認められていませんが、一部の分野では例外的に派遣形態での雇用が可能です。これは、一部の分野において季節によって大きな仕事量の変化がみられるためです。
本記事では、特定技能人材の派遣と派遣が可能な分野を紹介します。また、派遣元および派遣先が満たすべき要件、特定技能制度と労働者派遣法の関係を解説しますので、ぜひ参考にしてください。
外国人材の雇用をお考えの方へ
「初めての試みで、不安がいっぱい…」
「外国人材の採用経験はあるけど、苦い思い出がある…」
現在このようなお困りごとがありましたら、特定技能制度の利用実績が多いスキルド・ワーカーに安心しておまかせください。政府公認の海外パートナー企業と連携し、採用から入国手続き、受け入れサポートまでサポートします!
長年培ってきた採用ノウハウで、特に、介護・外食・飲食料品製造・宿泊・農業での外国人材のベストマッチングを実現します。まずはお問い合わせフォームから、ご相談ください。お困りごとに対して、最適なご提案をさせていただきます。
派遣雇用が可能な分野は農業と漁業のみ
原則、特定技能に従事する外国人労働者は、農業や漁業分野を除き派遣形態での雇用は認められていません。ただし農業・漁業分野は、季節に応じ仕事量が変化しやすいため派遣形態での雇用が可能です。
|
派遣OK |
派遣不可 |
|
農業 漁業 |
|
では農業分野と漁業分野で派遣雇用をした場合、どのような業務を行えるのでしょうか。
1. 【農業分野】派遣雇用で従事できる業務
農業分野において派遣雇用で従事できる業務は栽培管理や農作物の出荷や選別といった耕種農業全般、飼養管理や農作物の集出荷・選別などの畜産農業全般です。
また、農業の業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業等)にも従事できます。
ただし、耕種農業と畜産農業は技能試験が異なるため、それぞれ資格の取得が必要です。異なる区分の業務に従事することはできません。
2.【漁業分野】派遣雇用で従事できる業務
漁業分野において派遣雇用で従事できる業務は、漁業および養殖業です。漁業では、漁具の製作や補修、水産動植物の探索や漁具・漁労機械の操作といった業務、養殖業では、養殖資材の製作や補修、管理のほか、養殖水産動植物の育成管理や収穫などが対象です。
また、漁業⼜は養殖業に従事する⽇本⼈が通常従事することとなる関連業務であれば、外国⼈も魚の加工業務に従事することができます。漁業に従事する日本人と加工業務に従事する日本人が別部門であれば、外国人は加工部門の業務ができません。
ただし、漁業と養殖業は技能試験が異なるため、それぞれ資格の取得が必要です。異なる区分の業務に従事することはできません。
派遣雇用にあたっての条件
特定技能外国人を派遣雇用するためにはいくつか必要な条件があります。まず、人材を派遣する派遣元事業者と、人材を雇用する派遣先事業者のどちらにも必要な条件は以下の通りです。
- 関係法令の遵守
- 支援の実施
法令遵守はもちろんですが、特定技能外国人が円滑に安定した活動を行えるように日常生活や社会生活において支援をしなければなりません。例えば以下のような項目が挙げられます。
- 労働法令を遵守しているか
- 外国人を支援する計画が適切であるか
- 外国人を支援する体制があるか
- 雇用契約が適切であるか
- 社会保険や税金を正しく納めているかどうか
- 非自発的な離職者が出ていを発生させていないか
- 技能実習生は特定技能人材の失踪がないか など
次に派遣元事業者と派遣先事業者それぞれに必要な条件について紹介していきます。
派遣元事業者に必要な条件
特定技能人材の派遣元事業者に必要な条件は、以下の2つが挙げられます。
- 特定技能外国人を派遣できる資格を持った事業者であること
- 農業と漁業分野に関連のある事業者であること
また農業と漁業分野それぞれでも派遣元事業者になるために必要な条件があります。
農業分野での派遣元事業者になるために必要な条件
農業分野での特定技能人材の派遣を行う場合は、上記の2つ以外で以下のいずれかに該当していることが条件です。
① 農業又は農業関連業務を行っている事業者
② ①又は地方公共団体が資本金の過半数を出資している事業者
③ ①又は地方公共団体が業務執行に実質的に関与していると認められる事業者 (①の役職員又は地方公共団体の職員が役員となっている等)
④ 国家戦略特別区域法第 16 条の5第1項に規定する特定機関(国家戦略特区 で農業支援外国人受入事業を実施している事業者)
派遣元事業者には、例えば農業協同組合や農業協同組合連合会、農業者が組織する事業協同組合などがあります。
漁業分野での特定技能人材の派遣
漁業分野での特定技能人材の派遣を行う場合には、以下のいずれかに該当していることが条件です。
① 漁業分野に係る業務⼜はこれに関連する業務を⾏っている者
② ①⼜は地⽅公共団体が資本⾦の過半数を出資している者
③ ①⼜は地⽅公共団体が業務執⾏に実質的に関与していると認められる者
(①の役職員⼜は地⽅公共団体の職員が役員となっている等)
※引用:新たな外国⼈材受⼊れ制度に関するQ&A(漁業)|農林水産省
漁業においての派遣元事業者には、漁協や漁業協同組合連合会などが挙げられます。
派遣先事業者に必要な条件
派遣先が特定技能人材を受け入れる際、派遣先に必要な条件は次の4つが挙げられます
- 労働や社会保険、租税に関する法令を遵守していること
- 過去1年以内に特定技能外国人と同様の業務にあたる労働者を解雇していないこと
- 過去1年以内に派遣先の責任により行方不明者が出ていない
- 欠格事由に該当しないこと
欠格事由には、5年以内の出入国や労働法令違反がないことなどがあります。また上記の条件は特定技能人材を受け入れる前と同様、受け入れ中にも満たし続けなければなりません。
派遣先事業者に必要な条件を満たさなかった場合の罰則
派遣先事業者が必要な条件を満たさなかった場合、「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。不法就労助長罪とは外国人労働者の不法就労に加担・助長したという罰則です。
① 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせる行為
② 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置く行為
③ 事業として、①及び②の行為に関し斡旋する行為
のいずれかを行い、唆し、又はこれを助けた場合が該当します。
※引用:特定技能外国人受入れに関する運用要領|法務省
例えば以下のようなケースがあります。
- 不法滞在者や被退去強制者を働かせている場合
- 出入国在留管理局から労働許可を得ていないにもかかわらず働かせている場合
- 出入国在留管理局から許可された範囲を超えて働かせている場合
例えば、観光ビザで入国したのにもかかわらず労働させる、といったケースがあります。また出入国在留管理局から許可された範囲を超えて働かせている場合の例には、留学生のオーバーワークなどが想定されます。
注意しておきたい労働者派遣法3つのポイント
特定技能人材の派遣を行う場合、労働者の派遣元は労働者派遣法を遵守したうえでの対応が求められます。注意しておきたい3つのポイントについて、それぞれ見ていきましょう。
1. 派遣先管理台帳の作成
派遣先は、派遣就業を行う労働者が在籍する場合、派遣先管理台帳を作成しなければなりません。派遣先管理台帳には、派遣労働者の労働日や労働時間などの就業実態の記載を行います。また派遣先管理台帳に記載した内容の一部は、派遣元に報告するための書面としても利用されます。
派遣先管理台帳の記載事項
派遣先管理台帳を作成する際は、以下17の必須記載事項について覚えておきましょう。
- 派遣労働者の氏名
- 派遣元事業主の氏名または名称(派遣元事業所の法人名を記載する)
- 派遣元事業主の事業所の名称(支店の場合は支店名を記載)
- 派遣元事業無視の事業所所在地(電話番号も記載)
- 業務の種類や内容
- 派遣労働者が従事する業務にともなう責任の程度
- 派遣労働者が有期雇用派遣労働者か無期雇用派遣労働者であるか
- 協定対象派遣労働者か否か
- 派遣労働者が労働に従事した事業所名称と所在地、派遣就業した場所や組織単位
- 派遣労働者が労働に従事した事業所の所在地(電話番号も記載)
- 派遣元責任者に関する事項(電話番号も記載)
- 派遣先責任者に関する事項(電話番号も記載)
- 就業状況
- 派遣労働者から申し出を受けた苦情処理の状況
- 派遣労働者にかかわる社会保険や雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無
- 教育訓練を実施した日時および場所
- 紹介予定派遣に関する事項(紹介予定派遣の場合)
なお作成した派遣先管理台帳は、派遣労働者の派遣契約終了日から3年間、派遣先で保存しなければなりません。
2. 派遣先の対象地域
特定技能人材を派遣できる対象地域は、派遣元の責任者が日帰りで派遣労働者からの苦情処理を行える範囲の地域でなければなりません。このため派遣元と派遣先は同じ市内、同じ区内というように狭い範囲になる傾向があります。
3. 派遣期間
特定技能外国人でない場合でも、派遣先事業者は、派遣元から3年の派遣可能期間を超えて労働者の派遣を受け入れてはいけません。派遣労働者が無期雇用であるなどの理由がある場合この規定は適用外となりますが、原則は3年間です。特定技能外国人の派遣期間も上記3年間の規程が適用されます。
もし3年以上、派遣形態での雇用を希望する場合には、過半数労働組合などの意見聴取を行ったあと、3年の期間限定で派遣可能期間の延長ができます。ただし派遣可能期間の延長をした場合でも、同じ人材で派遣を延長することはできません。派遣延長の際は、違う人材を派遣労働者として受け入れる必要があります。
しかし派遣先が同じ場合でも、派遣される課が異なるときには同じ人材を派遣してもらうことが可能です。また従来とは違う業務区分に派遣される場合にも、派遣予定の業務に関する特定技能評価試験に合格したあと、特定技能雇用契約にかかわる届出書の提出を行います。
特定技能人材を派遣するメリット
直接雇用によって特定技能人材を雇用する場合、同一地域内だったとしても別の事業者から転職という形で従事するのであれば、入国管理局に変更許可申請を出さなければなりません。
申請してから許可が出るまで2週間から1カ月程度時間がかかったり、審査手数料が発生するといった手間がかかります。しかし派遣であれば変更許可申請を提出する必要がありません。臨時的に人手が必要なタイミングでのみ、特定技能外国人を雇用できるのは派遣を利用するメリットです。
加えて特定技能人材を直接雇用する際は、業種ごとに協議会への加入が必要ですが派遣であれば不要です。これは派遣元事業者が協議会に加入するためです。
採用以外の入社までにかかる費用
求人広告の出稿や人材紹介会社の利用以外にかかる費用は、次のようなものが考えられます。
- 健康診断の費用:約25,000円
- 特定技能ビザの申請費用:約15~20万円
- 1年ごとの在留期間更新申請:2~5万円
- 海外在住の特定技能外国人の方を雇用した場合
- 入国渡航費:5~10万円
- 住居の準備費用:家賃全額
- 特定技能試験に合格していない場合
- 受験料:7,000円~
これらの費用は、外国人材本人から徴収することはできません。送り出し国のルールに基づき、費用のすべてもしくは一部を負担することが定められています。
特定技能外国人に対する必要な支援の内容
特定技能外国人に対しては、受入れ機関や登録支援機関が支援を行うことが義務付けられています。特定技能外国人を雇用する場合には、義務的支援が多く定められているので、担当者を任命するなどして適切に対応しなければなりません。
たとえば、特定技能外国人に対しては、入国前の生活ガイダンスを行います。生活ガイダンスは特定技能外国人本人が理解できる言語を用いて行う必要があるでしょう。
その他にも在留中の生活オリエンテーション、外国人からの苦情や相談への対応、各種行政手続きについての情報提供や付き添いなども本人が理解できる言語を話せる人が行う必要があります。
特定技能外国人と定期的な面談をしたり、必要に応じて行政機関へ通報したりすることも支援の一部です。
これらの支援を受入れ先企業自身が行うことは難しいでしょう。多くの場合、「登録支援機関」と呼ばれる、法務省の認可を受けた機関に委託するのが一般的です。
特定技能人材の派遣は農業・漁業分野においてのみ可能
特定技能人材の派遣は原則認められていませんが、農業や漁業分野は例外的に派遣形態での雇用が認められています。農業や漁業の分野は季節によって仕事量が変化しやすいのが理由です。
特定技能人材を派遣形態で雇用するためには、派遣元事業者も派遣先事業者も一定の条件をクリアしていなければなりません。条件を満たしていない場合、法令違反となるだけでなく場合によっては罪に問われる場合もあります。
繁忙期のみ人手が必要となりがちな農業・漁業分野で、人材不足を解消するための手段として、特定技能人材の派遣を活用してみてはいかがでしょうか。
外国人材の雇用をお考えの方へ
「初めての試みで、不安がいっぱい…」
「外国人材の採用経験はあるけど、苦い思い出がある…」
現在このようなお困りごとがありましたら、特定技能制度の利用実績が多いスキルド・ワーカーに安心しておまかせください。政府公認の海外パートナー企業と連携し、採用から入国手続き、受け入れサポートまでサポートします!
長年培ってきた採用ノウハウで、特に、介護・外食・飲食料品製造・宿泊・農業での外国人材のベストマッチングを実現します。まずはお問い合わせフォームから、ご相談ください。お困りごとに対して、最適なご提案をさせていただきます。